飲食店で働く中で、ちょっと “謎” な単語あったりしますよね。
前回、”デシャップ” や “バス” などの謎単語を簡単に解説させていただきましたが、今回もその続きです。
『ノーショー』『ダスター』『やま』などなど、前回紹介出来なかった単語を、また50音順で解説させていただきます。
それではいってみましょう。
ノーショー?ダスター?やま? 特有の飲食業界用語 かんたん解説
あにき・おとうと
食材や飲材など消費期限のあるものに対して、古いものを『あにき』、新しいものを『おとうと』と呼んだりします。数日から1日でダメになってしまう食材などもある中で、先に作ったものから順に出していかないとせっかく仕入れた材料をお客様に提供することなく(お金に変わることなく)捨ててしまいかねないので、この管理は非常に重要です。ちなみに、先に作ったものを、後から作ったものよりも先に使う事は「先入先出」などと言われます。先に作ったものを冷蔵庫の奥にしまって、後から作ったものを冷蔵庫の手前に置いて、手前の後から作ったものを先につかってしまい、奥のものがダメになってしまう、、みたいな事のないように注意喚起する言葉です。
イーゼル A看板
正確には形の違うものではありますが、どちらも店頭の置き看板としてよく使われるものです。
『イーゼル』はもともと美術で絵を描く時などに使われる道具で、キャンバスを立てかける時に使われるもので、3本脚が一般的。飲食店では作成した看板をたてかけて使いますね。『A看板』も同様に置き看板として使われ、4本脚で開いた状態を横から見た時の見た目がアルファベットの “A” に似ているのでそう呼ばれます。
A看板は盤面が土台と一体化しており、一方イーゼルは土台に別途盤面を置くタイプなので、盤面を変えたい時の手間が若干異なります。曜日や時間帯によっていくつかの異なる看板を店頭に置きたい場合などは、イーゼルタイプの土台に必要に応じた看板を適宜設置していくのが良いのかと思いますね。
かわ(プッシュ)
「おすすめ」の意味で使われたりします。由来に確証は全くありませんが、察するに、後述する “品切れ” を意味する『やま』の単語が先に使われている中で、相対する意味合いの強い “おすすめ” の単語に対して何となく逆っぽい(山に対しては川でしょう)みたいな感じで使われ始めたのかなぁ、と思っております。洋食系のお店では横文字っぽい『プッシュ』の単語が同じ意味で使われることもあります。
ちなみに、飲食店における “おすすめ” にはいくつかの理由があります。まずは本来のおすすめの意味に最も近い〈すごく良いものがはいったのでおススメです〉〈すごく美味しいからおススメです〉の意味。他には〈たくさん作ってしまったからダメにしないために売ってほしい時のおススメ〉もあります。また、〈ダメになる期限が近いから早いうちに売ってほしい時のおススメ〉の意味合いもあります。
ただ、ここですごく注意してほしいのは粗悪な商品をお客様に売りつけるような “おススメ” は飲食店の信用がなくなってしまうのでやめてほしいです。あくまでも、自信をもってお客様に出せる商品をおススメする姿勢で自分たちのお店の商品に誇りを持っていきたいものです。
シズラー
チェーン店のSizzlerさんとは違います。一度くらいは見た事のある人が多いのではないでしょうか。栓抜きが一体となっている銀色の器具で、王冠のついている瓶を開栓した後に再度フタをする時に使われます。炭酸飲料の気泡を逃がしにくい状態で保管できる、という便利道具ですが、例えばコーラの瓶を開栓後にシズラーでフタをして1日以上たつと、さすがに炭酸はけっこう飛んでしまいますので悪しからず。ニューシズラーという商品名がそのまま通名として使われていると思います。
ステーション
ざっくりと「作業台」を指して言う事が多いです。”Station” の英単語の意味で一番に来るのは『駅』だと思いますが『停留所』という意味もあります。この停留所のニュアンスが飲食店で使われるステーションの意味合いとしてしっくりくるかもしれません。中継基地みたいな感じで以下の用途でよく使われます。
●お客様のテーブルからバッシングしたお皿やグラスなどを洗い場まで持っていかずに一時的に置いて他の作業を優先する
●お客様が帰られたテーブルを清掃するための用具や、その後にテーブルセットするためのお皿やカトラリーなどを整理して置いておく
●お水やお茶など、リフィル用のポットやタンクを置いておく
など、サービスを円滑に行うための便利基地みたいなものですね。
もちろん、席数や業態によって適したステーションの数や大きさなどはあるので、内装設計時のお店作りの段階で現場オペレーションに精通した人が、設置における妥当性をしっかりと判断できるかどうかがとても重要です。
ダスター
テーブルの上などを拭く時に使うふきんの事を言います。素材は色々で、綿・麻などの布製のものや、不織布で作られたものなど様々です。不織布のものは使い捨てのような感じで使われることも多く、一日ないし数日で新しいものと入れ替えて使われるのが飲食店では一般的かと。「カウンタークロス」と呼ばれるものが良く使われます。フードコートなどのセルフサービスの業態でテーブルを拭く用においてある “青”とか “ピンク”とか “緑”とか “白”とかのふきん、分かりますでしょうか。アレです。
チップ
飲食店で “チップ” というと、サービスが良かった時などに既定の飲食料金以外にお客様から個人的にもらえるお金、の事かと思いますが、他の意味で使われたりもしまして、「お皿やグラスが一部欠けてしまっている状態」の事をチップと言ったりします。そもそもの英単語の意味に “かけら” という意味があるのでこのニュアンスで使われ、明らかに割れてしまっているお皿やグラスに対しては使いません。
「このお皿チップしてますけどどうしましょう?」「うーん、やすりで削ったらまだいけそうだから削ってみよう」とか「んー、、これはダメだね。怪我しないように捨てておいてください」という流れで使われます。
ノーゲス
「ノーゲスト」の略で、店内にお客様がゼロの状態の事。
現場ではよく閉店近い時間帯で全てのお客様が帰られているかどうかの確認で『ノーゲス??』とか使われます。そして、お客様が帰られた事の確認ができたら、お店の締め作業の進行が一気にスピードアップします。早く帰りたいのと、スタッフによっては終電がギリギリだったりする場合もあるので。。
ノーショー
こちらは飲食業だけでなく、ホテルや飛行機など事前に予約を入れて利用するサービス業にて使われるのですが、意味としては、『予約を入れていたのにキャンセルの連絡もなく予約者が当日いらっしゃらない事』です。日本語で『無断キャンセル』と同じ意味ですね。
昨今、ノーショーは社会問題化もされており、ペナルティも実施されるケースが多くなってきているので利用者の方々はお気を付けください。飲食店としては本当に死活問題なのでご理解を。。
ブリケージ
「お皿やグラスが割れてしまう事」を指します。『今月はなぜこんなにブリケージが多いのか、、』『皆でブリケージを少なくするようにオペレーションを改善していこう』といった会話がされますね。ドタバタとする飲食店のピークタイムで思わぬ事故により食器が割れてしまう事はやむを得ないことでもあります。ただ、このブリケージを如何に少なくできるかはお店の利益に大きく影響してくるので、店舗管理者は実態の把握と再発防止のオペレーション構築、スタッフへの意識向上など丁寧に対応していくことがとても重要です。お皿やグラスの値段も昨今上がっておりますし。。
やま(ダウン)
「品切れ」の意味で使われます。語源には諸説ありますが、山の頂上まで行くとのその先がないので終わりまで使い切ったみたいな意味合いで使われ始めた、とかとか。洋食系のお店では横文字っぽい『ダウン』の単語が同じ意味で使われたりします。『ダウン』も『やま』のニュアンスと同じような感じで、頂上まで行ってその先で “ダウン” といったイメージでしょうか。また、残数が少なくなった時には頭に数字をつけて使われたりもします。残り3個の商品なら、「3やま」「3ダウン」みたいな感じで共有されるので、オーダーを受けるウェイター役の人は要注意です。
リセット
リセット自体のざっくりとした意味は、”最初の状態に戻す事” で、飲食店では主に「テーブル上のセットをお客様を受け入れる最初の状態にする」の意味合いで使われます。お店によりその状態は様々ですが、取り皿やお箸、フォークやナイフ、ナプキンが置かれていたりメニューやカトラリーボックスが置かれていたり、またレストラン系だとグラスが置かれていたりもしますね。もちろん、テーブル上やイスなども綺麗にしたうえで、卓をお客様が迎えられる状態にする事を言います。
また、その際に必要な備品類(上記で示したような『お皿・お箸・フォーク・ナイフ・ナプキン・カトラリーボックス』などなど)のこと自体を指したりもします。
具体的には
『8番卓さん2名様でリセットしておいて~』
➡8番卓のテーブルを片付けて綺麗にして2名様用のセットをする
『3番卓さん次に4名様入るから4名用の “リセット” 作っておいて』
➡4名様分の必要カトラリー類(お皿やフォークなど)をまとめておき、いつでもセットできるように準備しておく
みたいな感じで使われます。
いかがでしたでしょうか。いくつかの謎単語の意味が分かりましたでしょうか。
ちなみに言葉は生きているので、日々新しい意味をもった単語も産まれてきます。また、仲間うちでしか通じない隠語みたいなものがあるのと同じように、ある飲食店の中だけで通じる単語、というものも数多く存在すると思います。日常的に使用している単語が、別の場所では全く通じなかったり、あるいはまったく別の意味で使われていたり、といったことも多くあるので色々な場所で働いたりする時は気をつけましょう。
ちなみに飲食店は、挨拶や数の数え方、掛け声、返事、オーダーの通し方、などお店独自で使われるような言葉もすごく多いです。また機会があればそんな単語も紹介していければと思いますが、今回はここまで。
いつもありがとうございます。

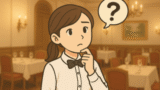
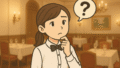

コメント